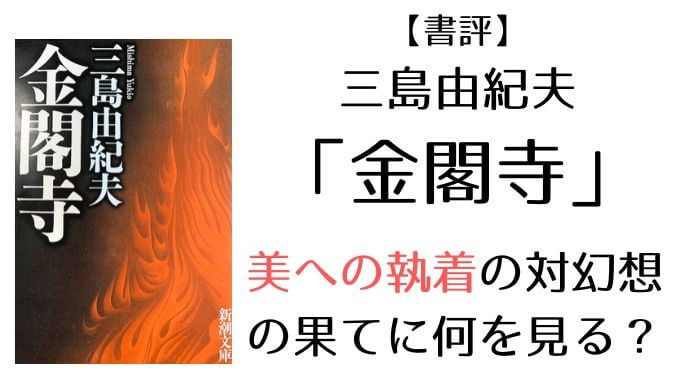こんにちは、霧島もとみです。
三島由紀夫の小説「金閣寺」を読んだ感想を紹介させていただきます。
金閣寺は昭和31年、三島由紀夫が31歳の時に発表した作品で、昭和25年に実際に起きた金閣寺焼失事件を題材に書かれました。三島由紀夫の代表作の一つとされています。
金閣寺は、あの金閣寺です。超有名ですね。焼失事件のことは今回始めて知って驚きました。今年の夏に見に行ったことを思い出します。
さてこの「金閣寺」は、吃音というハンディを背負い、自分自身の生を呪っていた学僧が金閣の美の魔力に魂を奪われ、遂には放火に至る…という物語です。
圧倒的な密度と火に炙られるような熱に満ちた難解な文章は読むのに力が必要で、まだ全部を飲み下せたとは感じられませんが、
世界との隔絶に苦しんだ男が求めたのは美との対幻想だった
ことを象徴する物語だと感じました。
主人公にとって金閣は美の象徴
主人公は生まれつきの吃音で、その事に大きなハンディを感じていました。
吃りは、いうまでもなく、私と外界とのあいだに一つの障碍を置いた。
また、父や母のほか、友人とも深い関係を持たない孤独な精神状態にありました。そんな主人公が特別視していたのが父から話に聞いた「金閣」で、自分とは異なる「美」の象徴として見るようになっていました。
この金閣への思いが物語の中で次第に変遷していきます。
・金閣=美への憧れ
↓
・空襲で金閣が失われる可能性に自分を重ねる
↓
・戦争が終わり、自分と金閣とに距離を感じる
↓
・金閣を焼くことで一体化しようとする
主人公の金閣への執着は相当なもので、何かあるたびに金閣のイメージが立ち起こり行動を止めます。例えば女性と関係しようという時に、金閣が思い起こされ不能になるとか。
主人公の世界との隔絶感や美に対しての葛藤が、金閣に具現化して現れているんですね。それほどに主人公の精神は歪んでしまっていたと言えるでしょう。
美への対幻想がもたらした犯行
主人公はこのように述懐しています。
私の関心、私に与えられた難問は美だけである筈だった。
主人公にとって最大の執着となっている美。
これについて、作品中で2つの見方が示唆されています。
一つは瞬間の美。
一つは不変の美。
動としての美については、大学の友人と尺八を吹くシーンでこのような記述があります。
美の無益さ、美がわが体内をとおりすぎて跡形もないこと、それが絶対に何ものをも変えぬこと……柏木の愛したのはそれだった。
生まれた瞬間に消えていく美とも言えるでしょう。
次に不変の美は、金閣が象徴しています。
時代を超えてそこに在り続ける美。瞬間の美と対比するものとして描かれています。
主人公がこだわったのは不変の美。最終的に主人公は友人との会話の中で「美は怨敵」とこぼします。自分にとって敵であると。それは自分自身と、そこに不変でありつづける美とが隔絶した存在であることを認めた言葉だと、僕は受け取りました。
美は怨敵だという隔絶と、
金閣を焼くことで一体化しようという欲。
一見矛盾するようなこの行為は、美への対幻想という見方をすることで理解できるのではないか。僕はそう考えました。
美は怨敵だというのは、本来は自分も美でありたかったという欲求の裏返しだと考えられます。しかし実際には自分は美と隔絶され、一体にはなれない。
それを解決する方法が美を破壊すること。
美を破壊することで、美を自分自身に一体化させるという構図を実現しようとしたのではないか。
速水和真さんの「イノセント・デイズ」を読んだ時、僕は「自分の存在を消すことで幻想への集合欲を満たす」と主人公の自殺を解釈しましたが、金閣寺で描かれているのはその逆の構図ではないかと。
自分を殺す、相手を焼くという逆の行為でありながら、その背景に「幻想への集合欲」の存在が共通するという考えです。
思えば、現実に起きる同様の事件の背景にも、似たような心理状態が働いているのかもしれません。
認識と行為の問題提起
物語の終盤、友人・柏木との会話の中で「認識と行為」についての問題提起がなされます。
これは突然に挿入されたものではありません。
物語を通じて「南泉斬猫」という禅話が何度か関わってくるのですが、これが「認識と行為」の問題提起の伏線になっているからです。
柏木はこう言います。
俺は君に知らせたかったんだ。この世界を変貌させるのは認識だと。
だがこの生を耐えるために、人間は認識の武器を持ったのだと云おう。
世界は不変だが、認識でそれを変貌させることができる。それは生きるための人間の武器だ、というメッセージです。
これに対して主人公は言います。
世界を変貌させるのは行為なんだ。それだけしかない。
世界を本質的に変化させることでしか、世界は変わらない、というメッセージです。
そしてこのやり取りを受けて、最後の金閣に放火するシーンで再度「認識と行為」の問題が提起されます。
放火の準備を整えた主人公は、「行為の一歩手前まで準備した」ことで行為が止まります。
してみると私の永い周到な準備は、ひとえに、行為をしなくてもよいという最後の認識のためではなかったか。
そう認識できた以上は、これ以上の行為は無駄でしなかいのでは。そんな認識に至ります。
しかし最終的に主人公は行為=放火を実行します。
金閣を燃やした後、主人公は「生きようと私は思った。」とだけ言います。
この展開をどう読めばいいのか、理解に苦しみました。
幻想が認識の中で完結するという展開を見せながら、最終的には行為に及ぶ主人公。その行為は、ある記憶がよみがえることによる突発的な衝動によるもの。その結果得られたものは「生きようと私は思った。」という簡潔な言葉だけ…。
しかし主人公の口から「生きようと私は思った。」という言葉が出るというのは、物語の中からは果たして考えられなかった真逆の事象でした。
これはつまり、主人公にとっては行為のみが決定的に認識を変えることが出来たというメッセージかもしれないと考えました。
認識によって世界は変えられると提示しながら、一方で行為でしか変わらない認識もある。大きな二律背反を突きつけられた、そんな気がしました。肉体を持つ人間の宿命の一つかもしれません。
…何だか良く分からないような感想になってしまいました。
それはつまり、まだ自分の中で理解できるだけの下地が整っていないという事だと思います。
ただ今の時点で自分がどう考えたのかを書いておくという意味では、とりあえず一定の価値はあるのかなということで書かせていただきました。
文学って難しいですね。でも刺激を受けます。
こちらもどうぞ。