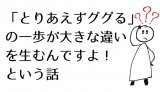こんにちは、霧島もとみです。
早見和真さんの小説「ぼくたちの家族」を読んだ感想を紹介させていただきます。
「ぼくたちの家族」は2011年に「砂上のファンファーレ」のタイトルで発売されました。その後2014年に石井裕也監督により「ぼくたちの家族」として映画化されたことでタイトルを変更して文庫化されています。
変わらない日常の中で家族というものを考えることが少ないなか、「家族とは何か」をあらためて問いかけた作品であり、かつ、家族という言葉に希望を感じた小説でした。
それでは感想を紹介させていただきます。
「ぼくたちの家族」はこんな話
父・母・兄・弟の4人家族が主人公です。
父:自営業
母:主婦
兄:結婚して家庭を持つ
弟:大学生で一人暮らし
家族の気持ちは離れ気味で、母がその仲を取り持ってきたという背景を持っています。そして、母が突然脳にガンを発症したところから物語は始まります。
これがきっかけで父・母が経済的に行き詰まっていた状況や、抱えていた借金が明るみになり、さらには余命も分からないと言われた母の治療にも目処が立たない…など、父と母が取り繕ろっていた「普通」の家族の姿が音を立てて崩れていきます。
その中で、兄と弟とが、それぞれ父や母ーー家族のために出来ることを手探りで探していくというのが大まかなストーリーです。
日常の中で家族は一見当たり前のようなものに認識されがちですが、それは表面的なものに過ぎない。脆く崩れていく可能性をいつも秘めている。
では家族とは何なのか?
これを問いただした作品だと言えます。
僕も家族を持つ人間として、この問いを強く突きつけられた感覚を受けました。
「ぼくたちの家族」から響いたもの
家族への危機感
強く感じたのは、生活の基盤と考えていた「家族」というものが、ささいな事であっという間に崩れかねない脆さを内包しているという危機感でした。
もちろんその状況は様々ですが、人生においてどんな事態が訪れるかは誰にも予想できない以上、危険性はどの家族にもありうると言えるでしょう。たとえ可能性がどれだけ低いとしても。
というのも、僕にも危機を持った経験があったからです。
追い詰められた状況で家族と向き合い、その中で家族全体としてどうするべきなのか、自分はどうするべきなのかを考えざるを得ない状況になりました。綺麗事だけでは済まず、とにかく手当たり次第に方法を探し、手探りで進みました。
「自分にとって家族とは何なのか」という事も自分自身に問いました。
その時に「自分が大事にしなければならない人が家族だ」と考え、それまで家族と考えていた人間に対して離別を決意しました。これまでの自分の一部を切り離すような辛い決断でしたが、必要なことだったと考えています。
だからこそ家族というものを大事にしなければならない。今を大切にしなければならない。
その危機感を改めて感じました。
家族という幻想の力
この小説では、4人の家族が、最終的には家族の形を取り戻します。
ばらばらの点だった一人一人が危機を通じて少しずつ変わっていき、次第に線として繋がり、奇跡のように繋がっていく物語には大きな希望を感じました。
なぜ物語の家族はもう一度繋がれたのか。それを考えるとき、鍵になったのは兄・弟が持っていた「家族」という対幻想です。
二人は自分と家族を一つの共同体として認識していました。だから苦境にあっても、助け合わなければという心が芽生え、苦しみながらも行動できたと考えられます。
もしも「家族」という幻想がなければ、大事なのは自分自身だけになりますから、展開は大きく変わっていたでしょう。
「ぼくたちの家族」というタイトルにもそれが表れています。
これは兄が小学校の時に書いた作文のタイトルとして物語中に出てくる言葉で、「ぼくたち」という言葉にすでに対幻想が表れていて、そこに「家族」という概念が加算されています。
家族という幻想の力を持つことは、人間が生きる力になる。
この本能的ともいえる力を理解して上手く使っていくことで、家族というものをもっと素敵なものに出来るかもしれないと改めて感じました。
以上、「ぼくたちの家族」の感想を書かせていただきました。
比較的短めな小説ですが、家族というものを改めて考えるきっかけになる本だったと思います。
こちらもどうぞ。
▼速水和真さんの「イノセント・デイズ」の感想