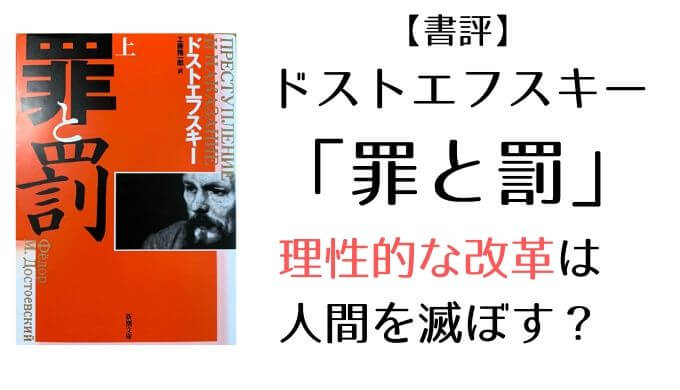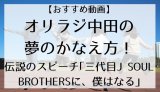こんにちは、霧島もとみです。
ドストエフスキーの小説「罪と罰」を読んだ感想を紹介させていただきます。
罪と罰は1866年に発表された長編小説で、ロシアの文豪フョードル・ドストエフスキーの代表作と言われている作品です。
読んだのは新潮文庫・工藤精一郎訳のもの。
古典文学も読んでみたいな…ということで読んでみた一冊でしたが、
今の僕では全部は理解できない…。
という難解な作品でした。
それでも読んだからには「罪と罰」とは何なのだろう?ということを考えてみたく、巻末の訳者解説の力を借りてまとめました。
「罪と罰」はこんな話
主人公は貧しい大学生(元?)のラスコーリニコフ。
舞台は当時のロシアの首都、サンクトペテルブルグです。
彼は一つの微細な罪悪は百の善行に償われるという理論のもとに、強欲非道な高利貸の老婆を殺害して財産を有用に転用しようと企てますが、偶然その場に居合わせた老婆の妹まで殺してしまいます。
その結果、殺人の罪の意識が彼に重くのしかかり、最終的には自首を選ぶ…というのがおおまかなストーリーです。
しかしこの話がなんと文庫上下巻で約1200ページ!
登場人物は半ば狂ったような人間ばかりで、会話も一見して支離滅裂。
脈絡の感じられない典型になかなか動かないストーリー。
また、ロシアの名前がただでさえ頭に入りにくいのに、同じ人物の呼び名が複数(愛称や正式名称など?)あったりしてますます分かりづらい。
読むのに疲れた…というのが正直な感想です。
これを読み切るには当時のロシアの時代背景や、共通文脈になっているキリスト教の理解(「ラザロの復活」のエピソードの意味など…)が必要になるのだと思います。その意味では、日本の文学と同じような気構えでは足りないのかもと痛感しました。
しかし世界文学にその名の高い「罪と罰」、その片鱗に少しでも触れたいと思い、思考を巡らせました。
「罪と罰」とは?
罪とは何か?解説文による解釈
下巻の最後には、訳者である工藤精一郎さんの解説があります。
その最後に次の一文がありました。
ドストエフスキーは「罪と罰」で人間の本性を忘れた理性だけによる改革が人間を破滅させることを説いたのである。
つまりこれが訳者が読んだ「罪と罰」の結論ということになります。
ここから読み取れるのは、
- 罪:人間の本性を忘れた理性だけによる改革
- 罰:人間を破滅させること
という構図です。
では次に、「人間の本性を忘れた理性だけによる改革」とは何なのか?作中でどのように描かれているのか?を考えなければなりません。
主人公の罪とは?
主人公は「一つの微細な罪悪は百の善行に償われるという理論」のもとに、強欲非道な高利貸の老婆を殺害して財産を有用に転用しようと企てました。
これは主人公が、「権力を継承によらず自分の力で奪い取った多くの恩人たち」が殺人や収奪を行ったが英雄として扱われていることを見て、このような行いは罪ではないとの理論を持っているからです。
この理論は作中で何度も登場します。
これが「理性だけによる改革」だと言えるでしょう。
ちなみに自首した主人公が自分の罪を認める場面に次の描写があります。
この一事、つまり自分の一歩に堪えられずに、自首したという一点に、彼は自分の罪を認めていた。
彼の論理的には、殺人を犯したこと自体は罪ではないと考えているんです。
では罪が何なのか?というと、自分が行ったその行為を理想のための行為として堪えきることができなかった、このことが罪だとしています。
しかし一方で殺人を犯したことを悔いる気持ちは彼を苛みます。それが「人間の本性」です。
ここから何が導けるのか?
人間の本性を忘れた理性だけによる改革、これが原理的に罪をはらんだ構図になっているという指摘ではないかと考えました。
「罪と罰」とは?
次に「罰」です。
罰については、作品中に「これが罰だ」という明確な指摘はないように思いました。ただ、近しいものとして、ソーニャという女性の次の言葉がありました。
苦しみを受けて、自分の罪をつぐなう、それが必要なのです。
これは一般的に言う「罰」の概念と一致するものです。
次に、主人公の変遷を考えてみます。
主人公は理性的に「罪ではない」と考えて犯行に至りました。
しかし実際に犯行に及んだ後は、罪を犯した意識にとらわれるようになり、自分の行いが「罪を超越するものではなかった」と認識します。
自分が体験してはじめて、罪が何かを目の当たりに理解・体感した…と僕は解釈しました。
そこに解説文からの「人間を破滅させること」が罰だという考えを合算してみると、この物語に込められた罰の姿が見えたような気がしてきました。
それが何かというと、
- 理性だけによる改革(殺人などの罪)は、人間の本性がどう判断するかは体験してみなければ分からない。
- だから理性だけによる改革を行うとする者は、自らの本性により、人間的な破滅にいたる可能性を常に持っている。それが罰である。
という事ではないかと。
この構図を、一人の人間の、一見なんでもないような殺人事件によって描き切ろうとしたのではないか。
僕はこのように考えました。
この本を読まれた方は、どうお考えでしょうか?
世界的に評価されている本であることは間違いないので、解釈に必要な知識と文脈をしっかりと育ててから、もう一度読んでみたいなと思います。
良く分からないながらも、刺激を受けた1冊でした。
こちらもどうぞ。

【書評】「蜜蜂と遠雷」活字から音楽が溢れてくる感覚を体験した

【書評】夏目漱石「こころ」で、個と全体性の矛盾の苦悩を読んだ話。

【書評】村上龍「半島を出よ」で物語に込められた共有する感覚を体験した