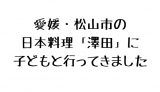これは#3000文字チャレンジの参加記事です。
3000文字チャレンジで連続する話を書くという事を思いつき、「フレグランス」「勝負」に続いての3作目です。
今回のお題で、既に行き詰まり感がものすごい状態になってきましたが、かろうじて形のようなものになりはしましたので、引き続き続けていきたいと思います。完全な遊びです。
それでは第3話、「三千世界と空っぽの井戸」をお届けします!
******
前回のあらすじ
三千世界という能力を突然手に入れた大学生・琢磨は、”勝負”の能力を見極めようとしていた。
しかし自分一人での分析に限界を感じ、友人である恭也の力を借り、競馬でチャレンジすることにした。
競馬の知識だけでなく、勝負事全般に長けた恭也の分析により”勝負”の能力を見極めた琢磨は、メインレースでブログキャップというムラっ気のある馬の単勝一点勝負に挑む。
その結果、馬券は見事に的中し、琢磨は大勝ちする。
それに対して恭也は、目先の出来事に左右されない勝負の心構えの大事さを琢磨に説いたのだった。
******
避暑地の山道を一台の車が走っていた。
一目見て高級車だと分かるその白い車の後部座席で、黒革のシートに深く腰掛けた男が電話で誰かと話していた。
張りと艶を感じる若々しい声だった。
「彼ーー三千世界の様子はどう?」
左手に持ったスマホから落ち着いた女性の声が聞こえてくる。
「変わりありません。先ほどまで、少し離れた古民家に連れていっていました」
「へえ、古民家。どうして?」
「井戸を見たいと言われたので」
「井戸を?」
男は口元を大きく緩ませた。男が笑う時の癖だった。
「なるほど面白い。”フレグランス”に”勝負”、次が”井戸”か。一貫性はないみたいだね」
「・・・」
「ん?山下くん、どうした?」
「彼のこと、会長がおっしゃるような、何か特別な力があるような人物には見えないのですが・・・」
「”勝負”の話はしただろう?」
「はい。でもその話と、私が実際に見る彼とでは印象が全然違います」
「山下くん、その感想はもっともだと思う」
男は声を弾ませて続けた。
「でも俺はね、普通の人間には見えない独自のセンサーを持ってる奴っていうのが昔から分かるんだよ。
だから分かるんだ。
あいつはヤバイ。
自分自身も分かってないみたいだけど、ものすごい噴流のようなものを感じる。
たぶん、生まれたての赤ん坊みたいなものだろう。これから感覚や言葉を獲得していったら、とんでもないものに化けるかもしれない、そんな気がするんだ。
想像するだけでワクワクしてこないか?」
「良く分かりませんが、会長がそうおっしゃるのでしたら、そうなんでしょうね」
「そういう訳だから、彼のことよろしく頼むね。
それにしても井戸かあ。山下くん、井戸って見たことある?」
「ホラー映画でなら見たことがあります」
「それ、井戸から人が出てくるヤツだよね。やっぱり井戸なんて、今や日常生活の中では見かけることはほとんど無い。生まれてから間がない彼なら、実物も映像も見たことはないだろう。イメージ湧きにくいだろうなあ」
「そのようでした。それで、彼の方から連れていって欲しいということになりました」
「いいね。いいよ。自分の能力に興味が出ているのは、いい傾向だよ。あと30分ほどでそっちに着くから、それまで休んでもらっててくれ」
「分かりました。門田会長、お気を付けて」
電話を終えると、門田と呼ばれた男は何か思いついたのか、メモ帳をカバンから取り出して単語を次々と書き殴り始めた。
*******
門田の別荘の一つがこの山間の避暑地にあった。
門田は別荘の駐車場に車を停めさせると、車から降りて別荘の反対方向に広がる山並を見上げた。窪地の向こう側にいくつもの山を見渡すことができる風景を、門田は気に入っていた。
「門田さん」
その背後から、門田を呼ぶ声が聞こえた。
門田が方向を振り向くと、最近知り合ったばかりの若い男が、別荘からの階段をゆっくりと歩いて降りて来るのが目に入った。
三千世界ーー蒼汰だった。
「やあ。蒼汰くん、変わりはないようだね」
「ええ。山下さんに良くしてもらっていますから」
「それは良かった。でも、わざわざ出迎えなんていいのに」
二人は軽く握手を交わした。
その手から伝わってくる熱量のようなものに、やはり不思議な感覚だと門田は感じた。
「門田さんに早く、今回の能力を見てもらいたいと思いましたので」
「それは嬉しいね」
「もう聞いていると思いますが、今回の能力は”井戸”です」
門田はそこで、蒼汰が左手に長い棒のようなものを持っていることに気付いた。
「それは何を持ってるの?」
「はい。玄関にあった金属製のステッキを借りたものです」
そう言うと、蒼汰は別荘の敷地内にある庭園の方向を手で示した。
「では早速お見せします。どうぞ、こちらへ一緒にお願いします」
******
「この辺りです」
蒼汰は立ち止まると、左手に持っていたステッキを右手に持ち替え、軽く掲げた。
「僕は”井戸”というものを知りませんでした。なので、お願いして実際の井戸を見せてもらい、井戸について教えてももらいました。そうしているうち、僕の中で”井戸”の能力が具体化される感覚がありました」
門田は蒼汰の話に耳を傾けていた。
「地面を覆う土や石や岩、その下を流れる水の存在を感じ取る感覚。そして、普段は地面の下にあって触ることができないその水を、地面の下から呼び出すことが出来るような感覚でした」
「なるほど」
「それともう一つ、感じるものがありました。それはまた後で話しますので、まずはこれを見てください」
「どうするんだい?」
「実際にここで試します」
「うん?」
ここは確かーーと門田が記憶の引き出しに指を差し込もうとしたとき、蒼汰は既に動いていた。
ステッキを両手でしっかりと持ち、力強くしっかりと、足元の地面へと垂直に突きこんだ。ステッキは表面の芝生に阻まれて深く突き刺さることはなかったが、その音と揺れとで、十分な振動が地面へと伝わったことを感じさせた。
蒼汰はそのまま動かず、じっと地面の芝生を見つめている。
そうしているうちに、ステッキを突き立てている箇所に水がじわりと滲んできた。滲んできたと思ったら、次の瞬間、勢いよくそこから噴水のように水が一気に吹き出してきた。
蒼汰は微動だにせず、吹き出した水に濡れるままに任せている。予想に反したのか、僅かに驚きの表情を浮かべていた。
門田は後方にいた山下を振り返った。
「驚いたね、山下くん。まるで弘法大師だ」
秘書の山下は、吹き出す水を避けながら返事をした。
「弘法大師・・・ですか?」
「”弘法にも筆の誤り”で有名なお坊さん、空海だよ。日本各地で、杖を突いて泉を湧かせたっていう伝説が残っている」
門田は蒼汰の方へ向き直った。
「蒼汰くん、ありがとう。能力は見せてもらった。これ以上濡れる必要はないし、一旦ここを離れよう」
そう言うと門田は蒼汰に近付いて肩のあたりを軽く叩き、移動を促した。
「すみません。思った以上に水が出てしまいました」
蒼汰のその言葉に、門田は少し困ったような、しかし面白がるような表情でこう答えた。
「謝らなくて大丈夫だよ。ここは、散水用の古い水道管が走っている場所だったんだ」
******
二人は身体を暖めるためのシャワーを浴び、着替えを済ませた。
光が存分に射し込むリビングのソファーに腰掛けて、二人は井戸についての会話を交わした。
門田が理解した内容はこうだった。
・地下にある水脈を感知できる
・水脈までの地盤の状態を感知できる
・エネルギーが溜まっている箇所に刺激を与えて噴出させられる
・人間の心理を井戸のヴィジョンに投影して見ることができる
・水脈、地盤のヴィジョンも見える
「が、そのヴィジョンが意味するところは分からない。それは”勝負”のときと同じだね」
「はい」
そう答えたあと、蒼汰は一言を付け加えた。
「ですが、水を蓄えた井戸のヴィジョンには安心感を覚えます」
「なるほどね」
門田はメモ帳を開き、絶えず手を動かしながら話を聞いていたが、その手がぴたりと止まった。
「ところで、君の目に僕のヴィジョンはどう見えている?」
「門田さんの・・・」
蒼汰は目を凝らして門田を見つめた。
蒼汰から見る門田の姿に重なるようにして、一つのヴィジョンが浮かび上がってきた。
「はい。
井戸は、深く掘られているように思えます。
硬い岩盤を越えて深く、根源的なところまで達しているよう。
井戸には澄んだ水が安定して蓄えられていて、いつでも水を汲み出すことができそう・・・といったように感じます」
門田はそれを聞くと、嬉しそうな表情を浮かべたまま、右手で頭を掻いた。
「どうだい。山下くん、聞いた?」
「・・・よくは分かりませんが、気のせいかお世辞が過ぎるように思います」
「いや、お世辞じゃないな。彼のヴィジョンは僕の自己認識とぴたりと一致していると思う。凄いよ。じゃあ今度は、山下くんのヴィジョンを見てくれるかな?」
蒼汰は小さく頷くと、今度は山下に向けて目を凝らしはじめた。
「ええと…水は安定して湧いているように見えます。が、細くて、門田さんと比べると浅い。不純物が僅かにですが、混じっている。
でもよく手入れされているような綺麗さがあります」
それを聞いて山下は、少々ふてくされた表情を浮かべた。
「門田さんよりも何だか印象が悪いですね」
一方、門田は笑いを浮かべていた。
「でも、実際のところはどう?見当違いかな?」
「いえ。悔しいですが、自分でも思い当たる節はあります」
門田は改めて、蒼汰を正面から見据えた。
「蒼汰くん。これは僕の印象だが、君の井戸のヴィジョンは人の欲求とその根源になっている経験や記憶を投影してるんだろうと思う。
『自分を掘り下げる』って言葉があるけど、井戸の深さはそのまま、自己認識の深さだろうね。
岩盤の厚さや硬さは、過去の記憶や経験に対しての距離や防壁だと思う。
井戸に溜まった水は欲求の性質だね。浅いところから出た欲求は濁りがちだし、深いところから滾滾と湧く水は確かなものであることが多い。
言われてみると、井戸と欲求の性質はよく似ている。驚いたよ」
気づきを楽しそうに話す門田とは裏腹に、蒼汰の表情は薄かった。
「それが井戸の、もう一つの能力なんですね」
「うん。だけど君にはピンと来ないと思う。なぜなら君はまだ発生したばかりだからだ。最初にフォーマットされている本能に由来するものがほとんどで、それ以外の水はまだ流れてないんだろう。
だからもし君自身のヴィジョンを見たとしたら、おそらく井戸は空っぽだ。そうじゃなかったかい?」
蒼汰は驚いた。
「はい…その通りでした。凄いですね」
「いや。僕は何も凄くないよ。凄いのは、君の観察と情報伝達の正確さの方で、僕はただそれを元に思考を深めただけ」
門田は手元のコーヒーに口をつけ、また話し始めた。
「で、どうする?」
蒼汰ははっとして顔をあげた。
何かを考え込んでいたようだが、すぐに元の表情に戻り、
「思いつかないです」
と言った。
「そうだね。一つ目の能力、本物の井戸を掘り起こす能力は今の日本ではあまり需要がないだろうね。昔なら物凄い価値があって、神様のように崇められただろうけど、今はインフラとして確立しているからね。
だから、試すとしたら二つ目の能力のほうだろう。どうかな?」
「門田さんがそう言われるのなら、そうだと思います」
「よし。じゃあ後はその能力を何に使うかだね。これは蒼汰くんが考えてみるといい」
「それなら、考えがあります」
「聞かせてもらってもいいかな?」
「はい。門田さんに見出してもらったヴィジョンの意味を踏まえて、人々を観察したいと考えています」
「ほう」
「僕の本能的なものだと思いますが、世界について知りたいという欲ーーのようなものを感じます。世界を構成する人々にどんな井戸のビジョンを見ることができるのか、それを知りたいです」
「見てどうするんだい?」
「そこまでは分かりません。でも、見ることで何かに気付くかもしれません」
「そうだね。それがいいと思うよ。では、善は急げだ」
門田は山下の方を振り返って言った。
「山下くん、彼を街へ連れて行ってくれないか」
******
蒼汰は驚いていた。
人々を観察することは、これまでの能力でも行ってきた事だった。
しかし、能力を自覚したうえで今見ている井戸の景色は、未経験の途方もない重たさを感じるものだった。
車で数時間かけて連れて来られた都会の街並み。
起点になる駅が近いのだろう、行き交う無数の人で溢れている交差点は、今にも干上がってしまいそうに感じる傷んだ井戸で溢れていた。
中には豊富な水量を湛えた深みのある井戸ももちろん見かけたが、あくまで少数で、大多数の人々は違った。
深さが全く無く、水脈に接続してもいない井戸も少なからず見受けられた。
彼らは雨が降るか、誰かに水を満たしてもらわなければたちまち干上がってしまうのではないかと、蒼汰には思われた。
「大丈夫ですか。顔色が優れないようですが」
隣にいた山下が声をかけた。
「人数が多すぎましたか?もし、身体に負担があるようなら、一旦戻って休んではどうですか」
「いえ、大丈夫です。特に負担は感じません」
蒼汰は続けた。
「・・・これだけ多くの人がいて、そのほとんどの井戸が今にも干上がってしまいそうな脆弱なヴィジョンなんです。
それが表す意味がどういうものかを想像したとき、急に恐ろしいような気がして、
その想像に目眩を覚えてしまいました」
「確か、井戸のヴィジョンは人の欲求と根源的な経験や記憶を表したものでしたね」
山下の口調は落ち着いていた。
「はい。それが門田さんの見立てでした。だとすると、この井戸が干上がろうとしている人達は、何に基づいて行動しているんでしょうか。それを考えると、僕は急に恐ろしくなったんです」
「それは蒼汰さんが考えることではないと思います」
「えっ?」
「蒼汰さんはまだ経験も知識も浅い。三千世界の能力以外は子どもと変わらないかもしれないんです。その状態であれこれ考えても徒労に終わったり、不要な心配をすることになりますよ。
とりあえず、考えることは門田に任せてもらえばいいと思います。
その橋渡しをするのが私の役目です。
蒼汰さんは、蒼汰さんにしかできない観察という行為を無心に行ってもらえばいいと思います」
そう言うと、山下は優しく微笑した。
蒼汰に張り詰めていた緊張感が弱まった。
「ありがとうございます。何か、気持ちが軽くなった気がします」
「それは良かったです。では、記録と報告は私がしますので、蒼汰さんは気が済むまで観察を続けてください」
「ありがとうございます。お願いします」
それから数日の間、蒼汰は山下に付き添われて人々の観察を続けた。
******
「そうか。多数の人間を同時に観察しても、身体に変調は見られなかったか」
電話の向こうから、門田の声が聞こえてくる。
話しているのは山下だった。
「はい。普段と変わりない様子でした」
「面白い。やはり彼は繋がっているね」
「繋がっている?」
「うん。考えてみたんだけど、観察から人の内面を正確に分析してビジョン化するって、ものすごく高度な処理だと思わないか?
一人や二人なら大丈夫かもしれないが、少なくとも多くの人間を一気に処理するようなタスクには相当な負荷がかかるはずなんだ。
もしパソコンだったら、CPUに相当な負荷がかかって発熱するような状態だよ。
そこで導かれる仮説は、彼はスタンドアローンの機体ではなくて、クラウド処理を行うためのインターフェース端末じゃないかって事なんだ」
「クラウド・・・ですか」
「そう。クラウドだよ。凄くないかい?」
「私にはまだピンと来ませんが、凄いんですか?」
「凄いよ。だってさ、クラウドだということは、繋がった向こうに処理をするためのサーバーが実際に存在してるっていうことじゃないかーー」
******
蒼汰は門田に与えられた部屋で、一人で休んでいた。
門田に出会ったのはわずか2週間前程のことではあったけれど、それから彼の世界は一気に変わった。
蒼汰は改めて、門田と自分自身について思考を巡らせていた。
彼ーー門田はあらゆるものを与えてくれた。
どこの誰とも分からない自分という存在を認めてくれ、衣食住だけでなく、三千世界の能力の分析にも惜しみなく知識と知性を注いでくれる。
”勝負”の能力で彼に恩恵を与えたことは確かだ。
だがそんなものは、成功者である彼の中では微々たるものに過ぎないだろう。
不思議でしかなかった。
一方、自分自身はどうだろうか?
自分を認めてくれている彼と、三千世界の能力を一緒に探っていくことは楽しいことだ。
自分一人ではたどり着けない思考へと導かれ、何だか自分自身のことが分かったような気になるからだ。
謎解きを一緒に解いているような感覚は楽しい。
それだけで良い。そんな風に思っていたはずだ。
でも”井戸”のヴィジョンがどうしても気にかかる。
門田の深くから湧き上がる欲求の井戸水は、それが彼の迷いのない行動の根源であることを強く感じさせた。
だが自分の井戸はどうだったか。水など見られず、ただの穴のようなものだった。
だとしたら僕の井戸は、雨のように降ってきた刹那的な水か、あるいは誰かに注がれた水を溜めることしか出来ないのではないか。
それにどんな意味があるというのだろうか。
僕自身の行動は、僕自身が望んでいることなんだろうか。
蒼汰の思考はそこで止まった。
彼は、杖を付いて地中から水を噴出させたことを思い出していた。
「あの時僕は、地中に流れる水を感じて、それに刺激を与えて噴出させた。
それと同じ様なことが、人間の井戸に対しても出来るとしたらーー」
蒼汰は机の上に置いてあったボールペンに手を伸ばすと、それを渾身の力で握りしめた。
ー 第3話「三千世界と空っぽの井戸」完 ー