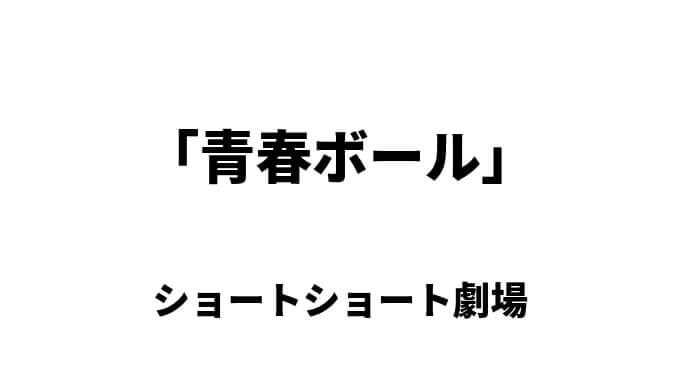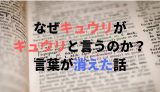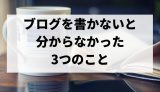高校三年最初の期末試験一日目、苦手科目だった物理に叩きのめされた僕は、その夜悪夢にうなされていた。
おがくずが詰まった大きな穴に放り込まれる夢だ。
足が、胸が、首が、口までもがずぶずぶと沈んでいき、やがて完全に息が出来なくなった。声にならない声で叫ぼうとしながら、最後の力を振り絞って右手を空に突き上げたーーところではっと目が覚めた。
意識が戻るといつものベッドだった。
違っていたのは、夢で最後に高く突き上げたその右手に、何か丸いものを握っている感触があったことだった。
見ると、やはり何かを握っていた。
それはほとんど透明でいながらどこか青っぽく、丸い形をししたものだった。力を込めて握ると、ゴムボールのような弾力で掌を押し返してくる。奇妙な物体だった。
試しに母親に見せてみたところ、
「何を持ってるって?パントマイムの練習?そんな冗談はいいから早く顔を洗ってきなさい」
と呆れた表情で、いつものルーティンを促されただけだった。父親も弟も同じ反応だった。
どうやらこのボール、自分以外には見えてないらしい。
通学途中、歩きながらそのボールを太陽にかざすと、中を光がゆらぎながら通り抜けてきた。
太陽から少しずらすと、晴天の青さがボールの中に溶けて穏やかな輝きを見せた。
印象的な青さだった。
友達を見つけたので、冗談半分にそのボールを投げつけてみた。すると、当たるかどうかというその瞬間に、ボールはすっとそいつに吸い込まれるように姿を消した。
驚いたが、そいつは何事もなかったように歩いていた。
少し速足になったようには見えた気もしたけれど、大きな変化は無かった。
呆然としていたら、また右手に何かを掴む感触があった。
僕の右手には新しいボールがいつの間にか握られていた。これは一体どういうことなんだろう。
それから僕はこのボールを他人にぶつけてみて、試すことにした。
とある男は、とたんに歩く速度が早足になった。
とある男は、急に叫びだした。
とある女は、きょろきょろと周りを落ち着きなく振り返った。
とある女は、穏やかな笑みを浮かべた。
どうやらこのボールを人間にぶつけると、行動に何かの変化を与えるらしい。
効果は十人十色で飽きることがなかった。
休日になると僕は人通りの多い街に出かけては、そのボールを見知らぬ人間にぶつけて楽しんだ。
しばらくして慣れてくると、次は、このボールは一体何なんだろうという興味が出てきた。
何人かの仲の良い友達にぶつけてみて、数日経ってから「最近何か変わったことはないか」と聞いてみた。
「特に何も」
「好きな子ができた」
「良く分からないけど自信がなくなった」
「今度の大会は、絶対に優勝するぜ」
「妙なイライラが増えた気がする」
反応は様々だった。
昔のアニメか何かで見たことがある「勇気を与える光」のようなものかとも思ったが、違ったらしい。
こうなったら自分で確かめるしかないと思ったのだけど、自分に投げてみても、何故かボールはすり抜けて反対側に落ちてしまう。特に変化も感じられなかった。
どうも自分自身には効果がないようだった。
ある日、学校帰りの歩道を歩いている時のことだった。
急に何か背中がぞわっとするような感覚を覚え、慌てて後ろを振り返った。
すると、一個のボールが僕をめがけてすごいスピードで飛んできていた。
あっ、と思うよりも早く、僕は反射的にそのボールを避けるように動いた。ボールは僕の横を通り抜け、僕の前を歩いていた別の男の背中に当たり、吸い込まれた。
僕は驚きを隠せなかった。
吸い込まれるように消えていった様子が、僕のボールのそれと全く同じだったからだ。
飛んできた方向に視線を向けると、同い年くらいの女子が僕の方を驚いた顔で見ていた。
僕は慌てて駆け寄った。
「今のボール、君が投げたの」
「えっ、そうだけど。そうか、今、見えてたんだよね」
女の子は慌てていた。僕は続けた。
「そう、見えてたんだ。それで僕の横を通り過ぎた後、別の人の背中に当たって…吸い込まれるように消えたんだ」
そこまで話したところで、僕は急に思い出した。僕のボールは自分以外には見えていなかったことを。
僕はいつものように、右手に僕のボールを掴み、その女の子に見せた。
「これ、僕もなんだ。見える?」
「うん。見える。君もボールが出る人なんだ…」
そこで初めて、僕はその子が同じ学校の制服を着ていることに気付いた。
僕たちは同じ「ボール使い」だった。僕たちは今までの経験や、試してみたこと、ボールについての考察を夢中で語り合った。
僕は今までにない充実感を覚えていた。
それからは度々会った。2人で街に出て、僕が前にしていたように通り過ぎる人間にボールを投げつけてみたり、ただ普通に遊んだりした。
気が付けば、いわゆる付き合うという関係のようになっていた。
ある日、彼女は僕に「僕のボールを当てて欲しい」と言った。
「ボールを当てられた人の変化を、自分自身でも体験して確かめたいの」
僕はそれに応えることにして、そっと優しく、ボールを彼女に投げつけた。
ボールを体に吸い込んだ後、彼女はしばらくぼうっとして、何かを一人で考えていた。
「何か分かった?じゃあ次には、僕にもボールを当ててみてよ」
ボールの代わりに飛んできたのは、彼女自身だった。
一人の人間の重さと柔らかさを突然受け止めて困惑している僕に、彼女は唇を重ねてきた。
柔らかく湿った感触と、漏れる息の生々しい匂いに衝撃を受けるなか、脳裏にひらめいたのは晴天の空に重ねた時のボールの色彩だった。
瞬間的に僕はボールの正体が分かった気がした。
「分かったよ、ボールの正体が」
彼女は言った。
「私も分かった」
「じゃあ、せーの!で言おうよ。」
せーの!と2人はタイミングをとり、
「恋」
「希望」
とそれぞれ口にした。
違うじゃん、と二人は笑い合った。
そう、僕は分かった気がしたのだった。今ここにある、2人が笑い合っているこの瞬間の空気が、感情が、きっとあのボールの正体なんだと。
僕たちは少し話し合ったあと、僕たちのボールに「青春ボール」という名前を付けることにした。
それから3日後、彼女からLINEが届いた。
「別に好きな人が出来たから、会うのやめよう。今までありがとう。バイバイ」
血の気が引くのを感じながら、
「そうか、これも一つの青春の形だな」
と僕はどこか納得していた。
僕のボールは、彼女に新しい青春を与えたのだ。
泣きたいくらい凄まじい効果だった。
予想外の形で青春ボールの力を見せつけられた僕の右手には、それ以来、新しいボールは出てこなかった。