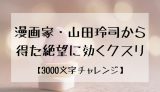霧島もとみです。
この記事はこぼりたつやさん(@tatsuya_kobori )が主催している3000文字チャレンジの参加記事です。
その中で「毎週更新されるお題を使って連続する話を書く」という事を思いつき、「フレグランス」「勝負」「井戸」と3つの作品を書いてきました。
本業が忙しくて休息している間に、「私を熱くさせたもの」「さくら」「10歳の頃」と既に3つの題が通り過ぎてしまい、めちゃくちゃ焦ってます。焦りました。焦り抜きました。
無理しないことが3000文字チャレンジのルールの一つなので焦る必要はないのですが、なんか寂しい気もしていて、ずっとモヤモヤしてました。
そこで、今回の記事で一気に「私を熱くさせたもの」「さくら」「10歳の頃」を書いてしまおうという企みを思いつきました。
それでは第4話、「三千世界と私が10歳の頃に熱く見た桜」をお届けします!
そしてこのシリーズは一旦終わらせていただきます・・・。
ただただ力不足です。
ちなみにこの話は15000文字を超えました。
正直に言います。
長いので読まないで下さい。
完全に自己満足の世界というか、自分へのけじめのような文章です。
前回のあらすじ
三千世界の力を持つ蒼汰は、事業家・門田の別荘で過ごしていた。
蒼汰は”井戸”の2つの力ーー「地下の水脈を感知して刺激する力」と「人間の心理を井戸のビジョンに投影する力」に気付き、それを門田に話した。
門田は洞察力をもとに、井戸のヴィジョンが人の欲求とその源泉になる経験や記憶の投影であると推定する。
蒼汰は門田のアドバイスに従い、街へ出向いて人々の井戸を観察するのだが、人々の渇いた井戸のヴィジョンに自分自身を投影して動揺する。
自分自身の欲求の欠落に恐れを抱いた蒼汰は、強制的に欲求を噴出させようと、三千世界の能力を自分自身に向けたのだった。
井戸の続き
蒼汰が三千世界”井戸”の力を自分自身に向けた時、初めは何の変化も起きることはなかった。
蒼汰の井戸の底にある地盤が岩のような固さを持ち、突き破ろうとした三千世界の力に軽々と耐えたからだ。
しかしながら蒼汰は、その岩盤の向こうから伝わってくる振動のヴィジョンに確かな水脈の存在を感じていた。
それは岩盤の向こうに、自分が認識していない経験や記憶が存在することを意味する。
だとすれば、過ごした時間が少ない自分自身には存在しないはずの記憶が、自分の中にあることになる。蒼汰の焦りはさらに強くなった。
自分の底に眠るものは、自分ではない何かーー。
蒼汰は震える意識の中で、三千世界の力をより収斂させ、もう一度岩盤に突き刺した。
確かな手応えがあった。
針よりも細い穴が岩盤を貫通し、そこからじわりと水が滲み出してきた。次いで滲みから水が僅かに湧き出してくると、その勢いは加速度的に強くなり、小さな噴水のように吹き出してきた。
その勢いは止まらなかった。
地鳴りのような音が響くと、それから一瞬遅れて、大きな爆発が起きた。
地下から押し上げられる水の勢いが爆発的に強くなり、蒼汰の井戸ごと、岩盤を吹き飛ばした。
それと同時に、膨大な情報が、蒼汰の意識に強制的に押し込まれた。断片的なヴィジョンが一瞬蒼汰に見えかけたが、すぐにかき消された。
蒼汰の意識は、洪水のように押し寄せる膨大な情報に押し流され、飲み込まれていった。
******
「意識は戻った?」
「いいえ。今日もずっと眠ったままです。これで4日の間、一度も目を覚ましていません」
「そうか」
電話で話しているのは、門田と山下の2人だった。
眠ったままの蒼汰は、避暑地にある門田の別荘で保護されていた。山下は別荘で蒼汰の様子を監視し、門田へ報告を行っていた。
「ひょっとしたら能力の一時的な反動かなと考えてたけど、4日はちょっと長過ぎるね。原因は違うところにあるのかもしれない」
「そうですね。確かに、倒れたときも能力での疲労という印象は受けませんでした。それよりも」
「それよりも?」
「はい。お伝えしたように、街の人々に干上がった井戸のヴィジョンを見たことのショックが大きい様子でした。その精神的な影響によるものかもしれません」
「干上がった井戸のヴィジョンか・・・」
門田は少し間を置いた。
「そうだ。僕は彼に話していた。”もし君自身のヴィジョンを見たとしたら、おそらく井戸は空っぽだ”と。そういえば、あの時の彼は少し考え込んでいる様子だった。
山下君の話だと、彼は街で見かけた人間に干上がった井戸のヴィジョンを見てショックを受けた。
おそらくだけど、そこで、彼は自分自身の井戸が枯れていることに漠然とした不安を感じたんじゃないだろうか。そして考えた。
なぜ彼らの井戸は枯れているのか。
なぜ自分の井戸は枯れているのか。
枯れた井戸に水を満たすにはどうしたらいいか。うんうん、なるほど。そういうことか」
門田は自分の思考を整理するように、電話に向かってぶつぶつと呟いていた。
山下は門田とのこれまでの付き合いから、こういう時は放置しておくのがベストだということを知っていたので、ただ黙っていた。
しばらくして、門田がはっきりとした口調で言った。
「山下君分かったよ。多分、彼は自分の井戸を掘ったんだ」
「井戸を掘った?どういうことですか?」
「最初に別荘で見せてもらった能力を覚えてる?彼は、地面の下にある水脈、実際には古い水道管だったけど、その存在を感じ取った。
それでどうやってかは分からないが、何かの刺激を与えて、水を噴出させたよね。それが1つ目の三千世界『井戸』の能力だったわけだけど、精神的な『井戸』のヴィジョンに対しても、同じような働きかけを行う能力があったんじゃないかな」
「はあ・・・」
「彼は自分の精神的な『井戸』の底のさらに向こうに、何かの存在を感じたんだろう。それで三千世界の能力で刺激を与えて、それを噴出させたという仮説が成り立たないだろうか?」
「・・・」
「いや、多分そうなんだよ。そうか。だからか。彼の意識の底のさらに向こうに流れている水脈が、きっと彼のベースになっている人間の記憶なんだ・・・」
山下は聞きながら、門田が話していることが理解できずに困惑していた。
「つまり、どういうことなんでしょうか」
「うん。大体分かった気がするよ。今日はそっちに行くから、そのときに話すことにしよう。ありがとう。それじゃあ、またね」
そこまで言うと、門田は一方的に電話を切った。
山下はしばらく唖然としていたが、いつもの事と言えばいつもの事だと思い直し、気持ちを切り替えて門田の到着を待つことにした。
蒼汰は変わらず、静かな表情で眠っていた。
******
門田が別荘に着いたのは、それから半日が過ぎた頃だった。すっかり夜になり、辺りは真っ暗になっていた。
門田はダイニングテーブルに山下と向かい合って座った。ポケットからスマホを取り出して少し触った後、画面を見るように促した。
「話の前に、まずこれを見てくれないか」
あるSNSのアプリが起動されていた。
「サーフェスノートですね」
「うん。そう。このアプリで写真を投稿する時、顔認識の機能を使えるのは知ってるよね」
「はい。顔から人物を自動判定して、タグ付けしてくれる機能ですよね」
「そうそう。で、昨日たまたま、このアプリで選ぶ写真を間違ったことがあったんだけどね」
そう言いながら、門田は写真の投稿の機能を立ち上げた。画面をスクロールさせて、スマホに保存している中から1枚の写真を選択した。
写真には、門田と蒼汰とが映っていた。
「さてこれで、写真をアップする準備が出来た訳なんだけど、この時点でもう自動的に人物のタグを付けてくれるんだ・・・おっ、出たね」
画面を見ていた山下が怪訝そうな表情を見せた。
「会長、これは・・・」
「二人の名前が出てるだろう?一人はもちろん僕、門田優だ。そしてもう一人の名前は、これは一体誰なんだろうね?」
画面上には、二人の名前が並んでいた。
門田優。
渡部正志。
「・・・知らない名前ですね」
「うん。僕も知らない。でも、蒼汰君のどの写真を選択しても、この”渡部正志”という名前がタグ付けされる。偶然とは言えない精度だ。そして調べたらすぐに分ったんだけど」
話す門田の表情に力が入った。
「この人物は、交通事故で半年前に死んでる」
****
それから門田は山下に自分の推論を熱く語った。
一通り門田が話し終わったところで、山下が口を開いた。必死に考えているのだろうか、艶のいい眉間にはっきりと皺が寄っていた。
「えっと・・・大体は理解できたとは思うのですが、確認させてもらっていいですか?」
「どうぞ」
門田は目を大きく開き、口元を緩ませた表情で答えた。
「蒼汰さんと渡部正志さんの外見が酷似している。見た目だけじゃなく、ホクロの位置や毛の生え際などの身体的な特徴まで完全一致している。これが1点目ですね」
「うん」
「次に、渡部正志さんが亡くなった時期と、蒼汰さんが出現した時期が時系列で並んでいて、かつ、それほど離れていない。これが2点目」
「うん」
「それで、蒼汰くんの言うように、彼がこの世界に突然出現したと仮定する。ですよね」
「うん。荒唐無稽な話だけどその仮定の理由は?」
「はい。それは彼がこれまで発現させた不思議な現象があるから。三千世界という現象自体が荒唐無稽なものであるのに、実際に現象として起きてしまっている事実があるから、ですよね」
「その通り。次は?」
「はい。もし彼が0からの発生だとすると、彼が出現してからの期間と彼の言語能力が矛盾する」
「そうそう」
「以上から、彼は渡部正志のコピーだと推測される」
「そう。その通り。ついでに言うと、コピーをベースに、新しい人格と三千世界へのアクセス権を与えられた存在だということになる」
山下は浅いため息をついた。
「全く、信じがたい話ですね」
「そうだね。僕もそう思う」
しかし門田の表情は、依然として明るかった。
「でもこの世の中なんて信じがたい話ばっかりだよ。今、僕や君が生きていることだってそうだ。生命ひとつ取ってみたって、こんなに複雑で膨大なシステムが組み上がって自律的に動いていることだって全く信じられない。それと同じだよ。
君は、君の右腕がなぜ動くのかを完全に説明できる?」
「・・・いいえ、出来ません」
「でも普通に動かしているよね。要は慣れだよ。まずは事実をありのまま受け入れて、それで何が出来るのかを考えればいい」
「分かりました。で、蒼汰さんをどうするつもりですか?」
「うん。彼が渡部正志のコピーだとして、彼の記憶がそのまま残っていることにしよう。けれども、蒼汰君の意識はそのことを全く認識していなかった。おそらくフィルターか、ロックのようなものがかかっていたんだろうね。
でも三千世界の”井戸”の力が、その制限を破壊して渡部正志の記憶を全て解放してしまった。
渡部正志が亡くなったのは21歳の時だ。
21年分の記憶が一気に吹き出したんだ。想像しただけで怖いよ。おそらく、蒼汰くんの意識は一気に押し流されてしまったことだろう」
笑ったまま、門田の眼が真剣に光った。
「実は、心当たりがある。その人物の力なら、きっと蒼汰くんは戻ってくることができるだろう。誰だと思う?」
「分かりません。腕のいい催眠術師とかでしょうか?」
門田は首を横に振った。そのままスマホを手に取って少し操作した後、画面を山下に向けた。
画面にはこう書かれていた。
”不定期ですが、今週は三千世界の館を開きます。
あなた自身のことと、あなた自身を熱くさせることをテーマにお話しします。
興味ある方はDMください。”
私を熱くさせたもの
「ありがとうございました・・・本当に。勇気を振り絞って、来てよかったです」
薄暗い明かりで照らされた小さな貸し会議室で、一人の女声が涙を流していた。
何か重たい荷物を取り除いてもらったような、晴れ晴れとした表情だった。
「それは良かった。力になれて嬉しかったです」
そう言いながら一人の男が、泣いている女性に手を差し伸べた。差し出された手を女性は両手で掴み、力を込めてゆっくりと握りしめながら、その手の先にいる人物を見つめていた。
大学生、琢磨だった。
一人の男がドアを開けた。終わりの合図だった。
女性は立ち上がって深々とお辞儀をすると、部屋の外へと出ていった。
男はドアを閉じると、照明のスイッチを押した。部屋中が明るく照らされる。
男は小さく首を振って琢磨に話しかけた。
「まだまだだな、琢磨」
「そうか?俺は良かったと思うけど」
そう言うと琢磨は机の上に置かれた封筒の中身を確かめた。
「1,2,3,4,5。5万円も入ってるぜ、恭也」
恭也は肩をすくめた。
「彼女の身なりなら、その5万円は思い切った金額だな。こんな若い、しかも素人まるだしの大根役者な男のトークに、よく5万円も払って帰ったよ」
琢磨は言葉を詰まらせた。
「・・・でも、話の内容は本物だからな」
「そう、三千世界様々だよ」
琢磨と恭也は、”三千世界の館”と称した相談室を開いていた。
三千世界の力を持つ大学生・琢磨が「せっかくの能力だから何かしたい」と話したのに対し、同じ大学に通う恭也が提案したのが相談室だった。
その目的は2つあった。
琢磨に経験を積ませることと、人脈を作らせることだった。
恭也の考えはこうだった。
「三千世界の能力が凄くたって、何も考えずに使えば”人生を人よりも楽に過ごすことができるツール”に過ぎない。
その能力を使って人を動かす事ができれば、より大きな影響力を発揮できるはず。
そのためには経験も必要だし、既に力を持った人物とのコネクションを持てればもっといい」
琢磨は恭也の考えに賛同しつつも、別に何か大きなことをしたい訳ではないと考えていた。しかし「経験は積んでみても損はないだろ」と言われて、それはそうだなあと思い、試しに開いたのがこの三千世界の館だった。
実際にやってみると、その面白さは琢磨の想像を超えていた。
相変わらず三千世界の能力は週ごとに変化していたが、違う角度で人の内面を見ることが出来るということで、常に新鮮な驚きを琢磨に与えていた。
それに、人の思考や経験というものが、琢磨自身でも想像していなかったような多面性や深さを持っていることに改めて驚いていた。
何より琢磨の言葉に影響を受けて、人が変わっていくことに喜びを感じていた。対価として支払われる謝礼ももちろん嬉しかったが、本能的な喜びを感じるのは、相談者の変化の方だった。
そんな琢磨を見ていて、恭也は満足していた。
人に影響を与える快感の強烈さが、次第に琢磨を変えていくだろうことを確信していたからだ。
「さて、今日はあと一人だ」
恭也はペットボトル入の茶を琢磨に手渡しながら話した。琢磨はキャップを開けて喉を潤すと、恭也に聞いた。
「最後は、どんな人なんだ?」
恭也は来客者の情報を琢磨に伝えていなかった。
できるだけ事前情報を減らし、新鮮な状態で会わせる方が能力を発揮できるだろうと考えていたからだ。
恭也はニヤリと笑った。
「驚くと駄目だから、今回は先に言っておこう。最後の一人は凄いぞ。門田優。若手経営者の中で最も注目されている人物だと言ってもいいだろう」
琢磨はその言葉に反応できなかった。
「知らない。誰だよそれ?」
「・・・女優のmisatoと交際している経営者だよ」
琢磨は飲んでいたお茶が変なところに入ったのか、急に咳き込んだ。
「・・・マジで?」
「多分、マジだ。彼のオフィシャルアカウントからのDMだったからな」
「なんでそんな有名人が、まだフォロワーも少ない怪しげなアカウントにいきなりDMするんだよ」
「それは分からないけど・・・初めての大物だ。でも誰だろうと気にすることはない。お前の能力は本物だ。いつもどおりで大丈夫だよ」
「そう言われても・・・やばい。なんか緊張してきた」
その時、ドアをノックする音が聞こえてきた。
「お、来たようだな」
恭也が照明を再び暗くした。
「それじゃ琢磨、行くぜ」
琢磨は無言で頷くと、背筋を伸ばして姿勢を整えた。引き締めた表情で顎を引き、両手を軽く握って机の上に置く。
恭也がドアをゆっくりと開けた。
「ようこそ。三千世界の館へー」
******
琢磨は訝しんでいた。
女優のmisatoと付き合っているという、ニュースや動画で見たことがある若い経営者が実際に来たことに最初は驚いたが、彼の意識はすぐに別のところへ向けられることになった。
門田優と一緒に部屋に入ってきた男、正確に言えばその背中に背負われていた男を見た時に、途方もない異物感を感じたからだ。
門田は、恭也に案内された椅子に、背中に背負っていた男を注意深く下ろして座らせると、自身はその横にパイプ椅子を持ってきて座った。
恭也と門田が何かを話しているが、琢磨の耳には全く入ってこない。
椅子に座ったまま眠っている男から目が離せなかった。
琢磨は無意識のうちに口を手で覆っていた。寒気か、それとも戦慄か、全身の毛穴が逆立つのを感じていた。
その琢磨の様子に門田が気付いた。
恭也と話していたときの自然な笑顔がすっと消え、真剣な顔つきに変わった。
「その様子だと、何か感じるものがあるみたいだね」
その声にはっとなり、琢磨は無言のまま、視線だけを門田へと向けた。
「そう。彼も君と同じ。三千世界の力を持っている男で、蒼汰君というんだ」
門田は静かな眼差しのまま言葉を続けた。
「実は少々困ったことになっていてね。あなたの力で、彼を取り戻してもらえませんか」
******
門田が琢磨に説明したことは、次のとおりだった。
・三千世界の力を持つ彼と偶然に知り合い、彼を保護することになった。
・彼は「自分自身は最近出現した」と言っていた。
・門田はそれを記憶喪失のようなものだと考えている。
・三千世界”井戸”の能力を自分に向けたようで、それからずっと眠ったままになっている。
・おそらく記憶が一気に吹き出して処理しきれなくなっている。
・彼の”私”を取り戻して欲しい。
「どう思う、恭也」
琢磨は、自身の隣に座っている恭也に小さな声で話しかけた。
恭也はあくまで琢磨を全面に出し、自身は補助役に徹していたのだが、この時は異常なシチュエーションであることを強く感じ取り、琢磨と一緒に門田の話を聞いていた。
「うん。おそらく本当の話だろうな。三千世界についての話は、俺がお前を通して知っている能力とほぼ同じように聞こえる」
「何てこった。俺だけの力じゃなかったんだな」
「まあ、別にお前だけじゃいけない理由はないだろう。別に何人いたって不思議な話じゃない。それよりも、この門田さんって人が何を目的にしているかだよ」
恭也はさらに声を潜めて言った。
「場合によっては、俺達も危険かもしれない」
「えっ・・・」
「まあ、それは極端な場合だけどな。よし。俺に任せてくれ」
恭也が門田に向かって話しかけた。
「少し質問させてもらってもいいでしょうか」
「もちろん。お願いに来たのは僕だし、何でも聞いてください」
「女優のmisatoさんと本当に付き合っているんでしょうか」
「ええと・・・」
門田は一瞬ためらいを見せたが、すぐに答えた。
「うん。付き合っているよ。もう半年になるかな」
「えっ、そんな前からですか」
「駄目だよ、君。そんなゴシップネタに本当は興味ないでしょう。もっと聞きたいことを、素直に聞いたほうがいい」
恭也は軽く唇を舐めた。
「・・・失礼しました。じゃあ、門田さんが知っている三千世界の力を順番に教えてください」
「僕が知っているのは3つ。フレグランス、勝負、井戸だね」
「実際に見たのは?」
「勝負と井戸だね。フレグランスは、彼から聞いた」
「どうして彼を保護しているんですか?」
「彼はこの世界のことを知らなさすぎる。生活していくだけのお金もなかった。彼に興味を持った僕が、お願いして来てもらったんだ」
「その動機はなんですか?」
「知りたいから」
「知りたいって、何を?」
「何でも」
「もう少し具体的に教えてください」
「三千世界という不思議な奇跡の正体を知りたいと思ってます。そのためにも、彼には目覚めてもらわないと困る」
「このまま目覚めなかったら?」
「目覚めるまで、方法を探していく」
「なぜ僕たちに頼もうと?」
「三千世界という言葉を使っていたのが一つ。”井戸”をキーワードにした能力を披露していたのが一つ。これは先週、僕の部下に実際に体験させて分かった。
もう一つは、これは僕の不思議な能力かもしれないけど、僕にはいわゆる”本物”の能力者が分かるんですよ。
今も実際に感じている。君の隣に座っている彼、霊能者ぶるにはあまりにも場馴れしていない彼が、間違いなく本物であるということを」
「分かりました。ありがとうございました」
そこまで話して、恭也は琢磨に囁いた。
「とりあえず害意はなさそうだ。何より、お前自身が感じてるんだろう?その眠っている男がお前と同類の存在だっていうことを」
「それは間違いないと思う」
「ならOKだ。これはお前にも、プラスになるような気がする。力を使っても大丈夫だろう」
琢磨は頷いた。
恭也は門田に向き直った。
「それでは、早速ご要望に答えさせていただきます。琢磨、今回は芝居はいらないぜ」
「分かった」
そう言うと、今度は琢磨が門田へ話しかけた。
「出来るかどうか分かりませんが、やれるだけやってみます」
「お願いします。ところで”井戸”はもう終わったと思うんだけど、今の三千世界はどういう力になってるの?」
「今の力は、”私を熱くさせたもの”です」
「それは興味深い。彼の意識を目覚めさせることができる?」
「分かりません。が、出来るだけやってみます」
そう言うと琢磨は、眠ったまま座っている男に視線を向け、意識を集中し始めた。
琢磨はそのまま三千世界の扉に手をかけて、その力を解放した。
******
「なんだこれ…」
琢磨は三千世界で開いた世界の光景を理解できず、混乱していた。
そこはーー蒼汰の内面にリンクした世界は、断片的なビジョンがひたすら無秩序に飛び交うばかりの世界だった。
これまで琢磨が”私を熱くさせたもの”の能力で覗いた世界は、形や大きさこそ様々だったが、ヴィジョンはある程度の繋がりと関係性を持ち、全体としては一つの群体を形作っている世界だった。
そこから琢磨は、”私”の核を形成する繋がりや、”熱くさせるもの”に強く反応するヴィジョンを三千世界の力で浮かび上がらせ、あるいは強く結合させ、その内容を相談者に伝えていた。
しかし蒼汰の世界はあまりにも乱雑すぎて、”私”も、”熱くさせるもの”も全く見当が付かない。
琢磨の脳裏に、門田の言葉が甦った。
(記憶が一気に噴き出して処理しきれない)
なるほど、情報としての記憶が存在しているが、紐づけがされていない、または何かのショックで紐づけが全て切れている状態なのかもしれない、と琢磨は考えた。
これではとても意識を戻すことは無理だ。
普通なら・・・と琢磨は呟いた。
核になる”私”が残っていれば、それをトリガーに整理することはある程度出来る。
しかし今回はその核が見当たらない。
膨大な数の無色のジグソーパズルを手作業で組み立てるような処理が必要だ。
シュレッダーされた書類を元の状態に戻すような作業とも言えるだろう。
気が遠くなるような時間と労力が必要で、とても出来っこない。
しかし、三千世界の力ならどうか。
材料は全て目の前に揃っている。
あとは材料同士の、膨大な繋がりの組み合わせを一つ一つ試していき、関連付けができるものを探して群体にしていくだけだ。
三千世界の力なら出来るかもしれない。
琢磨はそう感じていた。
これまでの能力も、日常生活の常識では考えられないものばかりだった。おそらく、それを実現させるには想像を絶する処理がバックボーンで行われているのだろう。
だとすれば、今回も可能じゃないか。
琢磨は覚悟を決めて、蒼汰の内面にリンクした世界にもう一度向き直った。
身を委ねよう。
三千世界の能力のままに。
きっと叶えてくれるはずだ。
琢磨は再び三千世界の扉に手を掛けて、”私”そして”熱くさせたもの”のイメージを強く描き、その身を能力に完全に委ねた。
琢磨の意識がすっと遠のいてゆき、また同時に、彩りを持った一つのヴィジョンとして形を変え、蒼汰のヴィジョンの中へと吸い込まれた。
******
<カチン>
最初は小さな音だった。
その世界の中で、小さなヴィジョン同士がわずかな結合を形成した。
それからしばらくして、別の一つのビジョンが引き寄せられるようにして近づき、
<カチン>
とまた小さな音を奏でた。
それから次の音が聞こえるまでには相当な時間を要したように感じた。そのまた次の音は、世界に小さな音が響いたことを忘れかけた頃に、
<カチン>
と音を立てた。
カチン
カチン
次第に音の間隔が短くなってきたかと思うと、次はぽつぽつと小雨が降るように連続して鳴り始めた。
やがて加速度的に音の頻度は高くなり、大きさも強くなっていった。
ヴィジョン同士の結合は次第に小さなまとまりを見せ、さらにその小さなまとまり同士が複雑に繋がりあい、一回り大きなネットワークを形成していった。
一つのネットワークが次の階層のネットワークを作りだし、それを何度も繰り返していく。
時間が経つと、そのネットワークはやがて2つの群体に集約された。
一つは相当な大きさを持ち、しかし、彩りを持たない群体。
一つは比べると微小だったが、彩りと輝きを持った群体。
最初に見せていたヴィジョンの無秩序さは姿を消していた。
そこで琢磨の意識が戻った。
琢磨は静かに目を開けると、ゆっくりと呼吸を何度か繰り返した。
その後、横に座っていた恭也に目線を送った。
「どうやら、出来たみたいだ」
「・・・上手くいったのか?」
「とりあえずは。でも、目覚めるにはまだ足りない」
そこで、門田が落ち着いた口調で尋ねた。
「何か動きがあったみたいだけど・・・蒼汰君の様子はどうかな?」
琢磨が答えた。
「はい。最初はどうなるかと焦りましたが、上手く三千世界の力が機能したように思います」
「ということは?」
「はい。おそらく意識は戻ると思います。でもーー」
琢磨は少し考える様子を見せた。
「でも?」
門田が尋ねた。
「動き出すには、もうひとつ、外部からの刺激が必要かもしれません。一旦完全に止まってしまった”私”を動かすには、最初のはずみが必要かもしれません」
「エンジンのセルを回すみたいな?」
「そうかもしれません。あ、ですが、ちょっといいですか?」
「何か気になることが?」
「彼には2つの”私”があるように感じました。記憶のヴィジョンが作るネットワークが、くっきりと2つのグループに断絶して存在していましたから。おそらく意識を失う直前の彼の”私”は、彩りを感じた小さな方のグループでしょう」
門田は頷きながら聞いていた。
「しかし、そちらの”私”には、はずみになるようなヴィジョンは見当たりませんでした」
「分かる気がするよ。では、もうひとつのグループには?」
「そちらには、はずみになりそうな”熱くさせるもの”は幾つか見つかりました。でも、そちらを刺激して発火させた場合、彼の中のバランスがどうなるのか・・・正直なところ想像ができません」
「でも、それしか方法は無い様な気がするね」
門田は覚悟を決めたように、真剣な表情で琢磨を見つめていた。
「その”熱くさせるもの”を、教えてもらえないかな?」
琢磨は少し考えた後、答えた。
「その前に、一つ聞いてもいいでしょうか」
「もちろん」
「彼は三千世界の能力を持っているんですよね?僕が持っているものと同じような」
「うん。君の力は全部は分からないけど、僕はそう考えている」
「なぜ彼の中には2つの”私”を感じるんでしょうか?」
「君は違うのか?」
琢磨は言葉に詰まった。
「どういうことでしょうか?」
「彼は、少し前にこの世界に発生したと話していた。君は、違うのかい?」
「僕にこの能力が宿ったのは、確かに少し前のことですね」
「そうじゃない。君には子どもの頃の記憶がある?」
「え?全部と言う訳じゃないですが・・・普通にあると思います」
「なるほど。でも、彼には少し前からの記憶しかないそうだ。彼に言わせると記憶喪失ではなく、彼自身が最近発生したかららしい。
僕には君が見た世界のことは分からないけど、おそらくそれが、2つの”私”が見えた理由なんだろうと思う」
「・・・」
琢磨は少し考え込んだ様子を見せていたが、すぐに元に戻り、話し始めた。
「ありがとうございます。何となくですが、分かった気がします。
それではお話させてもらいますが、最も”熱くさせたもの”として強く見えたものは、桜です」
「桜?」
「はい。どこか川沿いの公園、堤防の上の道にそって咲いている桜並木の中を歩いているビジョンに、強い熱さを感じます。
それと涙。
歩いているヴィジョンに涙が混じり、複雑で、強烈な熱さを感じます。
何か大きなものを失ったような感じも受けました。
それらが桜に強く結び付いた状態で保存されています」
「なるほど・・・」
門田は大きく頷いた。
「ありがとう。思い当たることはありそうだ。それでは早速、そこへ出かけてみることにするよ」
そう言うと、立ちあがって琢磨に握手を求めた。
「三千世界の力、見せてもらったよ。良かったら、これからも色々と助けて欲しい」
「こちらこそ。意識が戻ったら、蒼汰さんとも話をしてみたいです」
琢磨はわずかにぎこちない様子で門田の手を握った。
「あ、今日のお礼を忘れてたね」
門田はそう言うと上着の内ポケットを探り、封筒を一つ取り出した。
「それと、今日のことは口外無用にお願いします」
受け取った琢磨の手に、しっかりとした重みが伝わってきた。
だがそれ以上に、琢磨は門田という男の存在に意識を奪われていた。
「勿論です。ありがとうございました」
門田は蒼汰を連れ、会議室を後にした。
10歳の頃に見た桜
「桜、か・・・」
門田は車の中でスマホを触っていた。
後部座席に座り、せわしなく指を動かしている。表情は謎解きに夢中な子どものように楽しそうだ。
「あった。これだ」
そう言うと門田は、助手席に座っている山下にスマホを手渡し、画面を見るように促した。
「渡部正志くんのサーフェスノートで見た気がしてたんだ。ほら。4月になると同じ桜並木で写真を取ってアップしてる」
山下は画面の記事を目で追った。
土手に等間隔に並んだ万階の桜並木の写真に短い文書が添えられていた。
”今年もこの土手を通った。天気にも恵まれて満開の桜が溢れ出るように咲いて迫力が凄い。
この桜はいつも僕の琴線に強く触れる。
あの日のことを思い出し、決意を新たにさせてくれる。
桜と共に散った父さん。僕たちは今年も元気に桜を見ることができています。”
読んで行くと、前の年も、そのまた前の年も同じ場所に来ていることが伺えた。どうやら、渡部正志の父の命日が桜の季節で、その墓参りに行く時にちょうど桜並木の場所を通っているらしかった。
ある年の記事には、場所の名前も書かれていた。
花山川公園というところだった。
「この場所へ蒼汰君を連れていくんですね」
「うん。この桜はきっと蒼汰君の中にいる、渡部正志くんの意識に強く働きかけるだろう。投稿を読むと、彼が父親を亡くしたのは10歳の時だ。自分の他には病気がちな母親と、年が離れた妹二人が残された環境で、彼がどれだけの衝撃を受けて、どれだけの覚悟をしたかということは容易に想像できる」
「そうですね、相当なものだったと思います」
山下は、門田が自分を重ねているように感じられずにはいられなかった。門田が幼い頃に両親を亡くしていたことを知っていたからだ。
「彼は父親の死に衝撃を覚えた。そして桜の季節が来るたびに、ここで桜並木の下を歩くたびに、父親を思い出して決意を新たにしていた。その彼がもう一度桜並木を見て、感じるものがないとは思えません」
「うん。僕もそう思うよ」
「ですが、少し気になります」
山下は続けた。
「桜に刺激を受けるのは、あくまで渡部正志の記憶であるはずで、蒼汰さんの記憶ではありません。蒼汰さんの意識が目覚めるのでしょうか?それに、場合によっては、蒼汰さんではなく渡部正志の人格的が目覚めるという可能性もあるのではないでしょうか?
会長はどう考えられていますか」
「うん」
門田はゆっくりと頷いた。
「良く分からない」
「えっ」
「分からないよ。刺激によって目覚めるのが、蒼汰君か、渡部正志という人格なのかなんてね。
大事なのはとにかく目覚めることだよ。目覚めることで動き出す。そうしたら、蒼汰君だろうと、渡部正志だろうと、また関わりを持っていけばいいだけの話だ。
せっかく出会った三千世界という存在、僕はそう簡単には手放さないよ」
「・・・そうですか」
「山下君はどう思ってるの?」
「私ですか?
そうですね、できれば蒼汰さんとまた会いたいと思います」
「そうか」
門田は小さな笑いを浮かべながら同意した。
「実は、僕もそう思ってる」
******
昼下がりの空。
雲がほとんど見当たらない、吸い込まれるような青色に包まれていた。
時おり、強さを持った風が吹き抜ける。
その風は花山川公園の土手に咲く桜並木をごうと揺らし、満開を迎えていた花弁を惜しげもなく舞い散らせ、豪勢な光景を作り出していた。
その中を門田が歩いていた。
車椅子に座った蒼汰を押しながら、初めて見る景色を楽しむように、ゆっくりと歩みを進めていた。
痛んだアスファルトが車椅子を揺らす。
河川敷の公園からは花見客の騒がしい声が聞こえ、アルコールと焼けた肉が混じった独特の匂いが漂ってくる。
どこでもこんな光景が見られるんだな、と門田は嬉しく思った。
ゆっくりと歩きながら、門田も自分自身の中にある桜に想いを馳せていた。渡部正志がそうであるように、門田自身も桜に思い入れを持っていた。
自分自身にどんなことがあっても、毎年春になると、桜は咲く。
少しずつ形は変えながらも、同じ季節の同じ場所に、同じような光景が毎年繰り返される。
いつの頃からか、桜を見ると、ああ、1年が経ったんだなと強く感じるようになっていた。同時に、去年の自分自身からの変化を実感し、1年という時間の濃密さを振り返る機会でもあった。
さらに過去の記憶へと旅立つこともあった。
その時々の桜の光景とともに、それを見ていた自分自身の心象が甦ってくる。それを眺めることもまた、楽しいと門田は思っていた。
いつしか門田は蒼汰のことを忘れ、自分自身の桜を見ながら歩いていた。
その時、門田の手に強い力が伝わってきた。
押していた車椅子の車輪が道路の凹みに落ち込み、急ブレーキがかかったのだ。意識を自分自身の記憶に向けていた門田は反応が大きく遅れ、座っていた蒼汰を車椅子から前方に押し出す格好になってしまった。
蒼汰は前のめりにバランスを崩し、そのまま道路に倒れ込んだ。
門田が慌てて蒼汰に駆け寄り、体を起こした。
蒼汰の眼がうっすらと開いていた。
ぼんやりとした表情のままだったが、確かに眼がうっすらと開き、桜の方に向けられていた。
「痛い・・・」
蒼汰の口から小さな呻きが聞こえた。
「だから言っただろう。段差があるから、桜ばかり見てたら危ないって・・・」
「兄ちゃんが悪い見本を見せたんだから、お前はこけないようにしなきゃ駄目だぞ・・・」
門田は蒼汰の体を抱き抱えたまま、優しく話しかけた。
「やあ。眼が覚めたのかい?ごめんよ。僕が段差に気がつかなくて、君を転げさせてしまった」
蒼汰の眼が、桜から門田の方へゆっくりと向きを変えた。
「いえ、こちらこそ体を起こしてもらって。ありがとうございます。でも、まだ力が入らない」
「気にしなくて大丈夫だよ」
そういうと門田は力を入れ、蒼汰立ちあがらせると、そのまま車椅子に座らせた。その正面に中腰で立つと、蒼汰と目線を合わせて話しかけた。
「僕は門田という。君は?」
「僕は・・・渡部正志といいます」
門田は表情を変えなかった。
優しさが感じられる笑顔のままで、蒼汰を見ていた。
「嘘を言っちゃ駄目だよ。蒼汰君、眼が覚めたんだろう?」
それを聞いて、蒼汰が門田につられるように笑みを浮かべた。
「やだなあ、驚かそうと思ったのに。どうして分かったんですか?」
「表情が、僕のことを知ってる、安心したって教えてくれてるからだよ」
「あ、やっぱり出ちゃってますか」
蒼汰はそう言った後、表情を改めて門田に向き直った。
「ご心配をおかけしました。それに、助けてもらってありがとうございました」
「礼なんていらないよ。君は、僕の大切な趣味の一つだからね。でもまあ、何にしても意識が戻って良かった。嬉しいよ」
門田は立ちあがった。
「ところで、さっき君は、自分のことを渡部正志と言った。ということは、彼の記憶と君の意識とが繋がったって事なんだろうか」
「おそらくは。でもまだ、鮮明に見えている訳ではないのですが・・・」
蒼汰は桜を眺めながら続けた。
「この桜並木の光景、花見の匂い、吹き抜ける風と、靴越しに感じてた道路の痛み具合。それらは記憶として、自然に連想されています。
そして、胸に強く訴えかけてくる、10歳の時の悲しみと決意。それが今は、はっきりと感じることができます」
「うん。それが、君の”私を熱くさせるもの”ということのようだよ」
「熱さ・・・。僕にはない感情と記憶でした。きっと彼にとって、かけがえのない大事なものだったんですね」
「熱さも感じられる?」
「はい。上手く言葉には表せませんが、ぐっと来るものがあります」
門田は右手を差し出しながら言った。
「蒼汰君、おかえり」
蒼汰が同じく右手を差し出し、門田と握手を交わした。
「ありがとうございました」
蒼汰がそのまま言葉を続けた。
「もう少しだけ、ここにいて大丈夫でしょうか。僕の中にいる彼、渡部正志に、ここの桜をもう少し見せてあげたいんです」
「もちろん。じゃあ、しばらく散歩してみようか」
門田はそういうと、再び車椅子の後ろに戻って押し始めた。
春の陽気と喧騒が、桜の下を歩く二人を優しく、ゆっくりと包んでいた。
おわりに(言い訳みたいなもの)
と、いうことで、とりあえず話を一旦終わります。
書いていないこと、書ききれてないことは山ほどありますが、それ以上に「小説的な連続した話は、今の自分の文章力では書けるものじゃない」ということを死ぬほど痛感したので、ここで止めることにします。
はっきり言いますが(多分誰もここまで読んでいないと思うので・・・)、作品としての完成度は度外視した、とにかく「書くこと」だけを優先した内容のため、正直なところとても読めたものじゃないと思うんですよね。
でも、これを読めるレベルに仕上げるのは、まだまだ時間と労力がかかるし、何より最初に立ち返って構想を練るところから始めないと駄目です。
それはもはやブログではないし、ブログの一記事でもないと思うんです。
そういう文章も書いてみたい気持ちはありますが、まずはブログを書くのが今のところの優先事項です。
他に書きたいネタ、書かなければいけない・・・と勝手に思っているネタもあります。
なので、三千世界の話はいったん筆を置き、元々のブログ記事としての#3000文字チャレンジや、それ以外のブログ記事に力を注いでいきます。
あーーーーーーー。
疲れたけど。
その割にはちゃんとしたものは書けてないけど。
面白かったです。書いてて。
それだけでも#3000文字チャレンジとしては、オッケーですよね。きっと。
と言う訳で、恥も外聞も捨てて、せっかく書いたものなのでアップさせていただきます。
そして、もしもこの長い記事を最後まで読んでいただいた方がいらっしゃったのなら。
心の底から、お礼を言わさせていただきます。
ありがとうございました!!!
めっちゃ救われます!!
こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。
さあ、面白いものを書くぞ!!