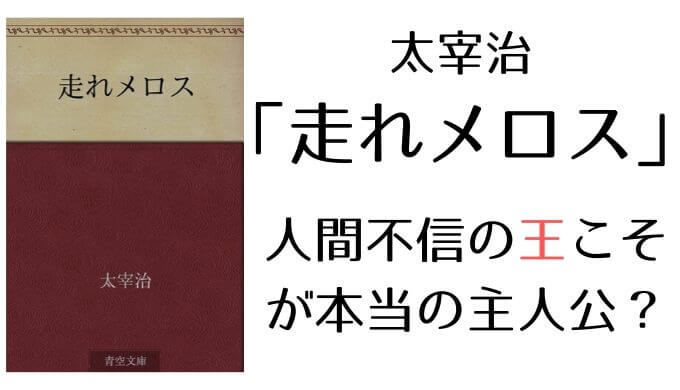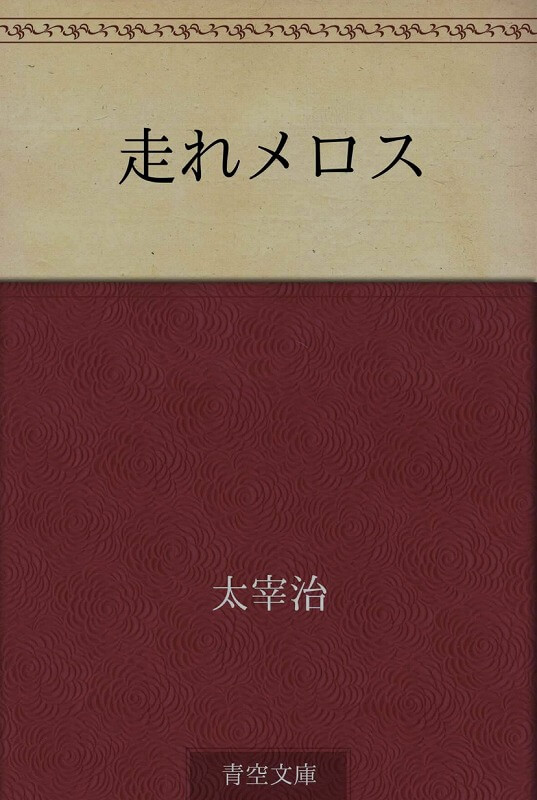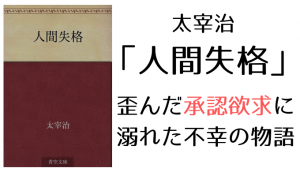霧島もとみです。
太宰治の小説「走れメロス」の感想を紹介させていただきます。
昭和15年に発表された短編小説「走れメロス」は、国語教科書に採用されていることなどもあって抜群の知名度を誇る小説です。友情ゆえに友の身代わりになった男と、身代わりになった友のために走る男。人を信じる素晴らしさ、友情の素晴らしさを描いた作品とされています。
メロスの緊迫した描写の迫力がすさまじく、また、講談を聴いているようなテンポの良い文章で、あっという間に読めてしまう面白い小説でした。
短編小説だけあって話自体はとてもシンプルなため、この記事では「こんな小説でした」という紹介は省略して、私が読んで考えたことを書かせていただきます。
ちょっとひねくれたモノの見方かもしれませんが、ご容赦ください。
なぜ太宰治は「走れメロス」を書いたのか?という疑問
太宰治の小説を「斜陽」「人間失格」と読んできて、次いで「走れメロス」を読んだ時にまず感じたのが「太宰治の人物像と違う話だなあ」という事でした。
予想外に美しい、青臭い話だなあと。
「クサい」ってやつですね。
「斜陽」「人間失格」に自伝的な要素が含まれているとすると、太宰治の人物像はメロスとはまるで逆で、他人が何を考えているか分からない、理解できない、そこに苦しんでいる人間という風に書かれています。
他人の考えが分からない、理解できない人は、他人を信じることも出来ないでしょう。
「俺はお前が何を考えているか全く分からないが、心の底から信頼しているぜ!」
という意味不明にアツい人間ではなかったはずです。
そんな人がなぜ「人を信じる物語」を書いたのだろうか?本作を書くモチベーションはどこから生まれたのか?
「走れメロス」を読み終わった時に、この疑問を強く感じました。
この疑問の答えとして考えたのが、この作品の主人公は「メロス」ではなく、「王」ではないかという仮説です。
主人公はメロスではなく「王」ではないか?という仮説
「走れメロス」はメロスの一人称で書かれた物語で、メロスを中心に物語は展開します。だから当然にメロスが主人公だというように思っていました。
一方、「王」は人を信じない悪人として描かれています。人を信じられないゆえに、次々と身内を殺し、臣下を殺していくという邪知暴虐の王だとされています。
メロスとセリヌンティウスが友情を貫いたことに王は心を打たれ、改心するというのが本作のストーリーなので、メロスとセリヌンティウスが物語の中心であり、王はオマケというか友情を演出するだけの仕掛けのような印象を受けました。
しかしこれでは、太宰治がこの物語を書いた理由が腑に落ちません。彼はそんなに「友情最高!!」というような素敵なナイスガイなのでしょうか?
そこで「王」が主人公だと考えるとどうでしょうか。人を信じない、それ故に人を次々と殺していくという精神性は、太宰治のそれを投影したと考えられないでしょうか。
太宰治こそが本作の「王」=主人公という発想で読むと、物語の印象は変わります。
人を信じられない王が暴虐の限りを尽くす。メロスとセリヌンティウスが友情の姿、人を信じる姿を王に示し、王が改心をする。王の精神性の変化の物語になってきます。
ここでもう一度「なぜ太宰治はこの作品を書いたのか」を考えると、その理由が浮かびあがります。
現実で人を理解できず容易に信じられない太宰治が、一方では人を信じたいという願望を強く持っていて、その葛藤がこの作品を書かせたのではないか?という理由です。
もしそんな葛藤を抱えていたとしたら、精神が引き裂かれるような苦しみを抱えていた事と想像できます。その葛藤と苦しみのエネルギーが、お互いに殴り合って許し合うという、過剰にクサいともいえるような本作を書かせたのではないでしょうか。
また、主人公が王=太宰治と過程すると、本作の出だしにドキっとさせられます。
そこにはこう書かれています。
メロスは激怒した。必ず、かの邪知暴虐の王を除かなければならぬと決意した。
自分自身を除かなければならぬ、そう宣言しているように思えます。非常に強烈な、しかし悲しいメッセージです。
王=太宰治=主人公説もそう外れたものではないのかもしれません。
そんな感想を持ちました。
「走れメロス」は短いながら、圧倒的な没入感、美しい友情の姿など際立つエッセンスが感じられる小説です。
メロスを主人公として友情の姿に感動するもよし、王を主人公として葛藤に苦しむもよし、いずれにしても価値のある時間を過ごすことができると思います。
AmazonのKindle版では青空文庫版を無料で読めるので、まだ読んだことがないという方は一度読んでみてはいかがでしょうか。
▼太宰治作品の他の書評も書いています▼